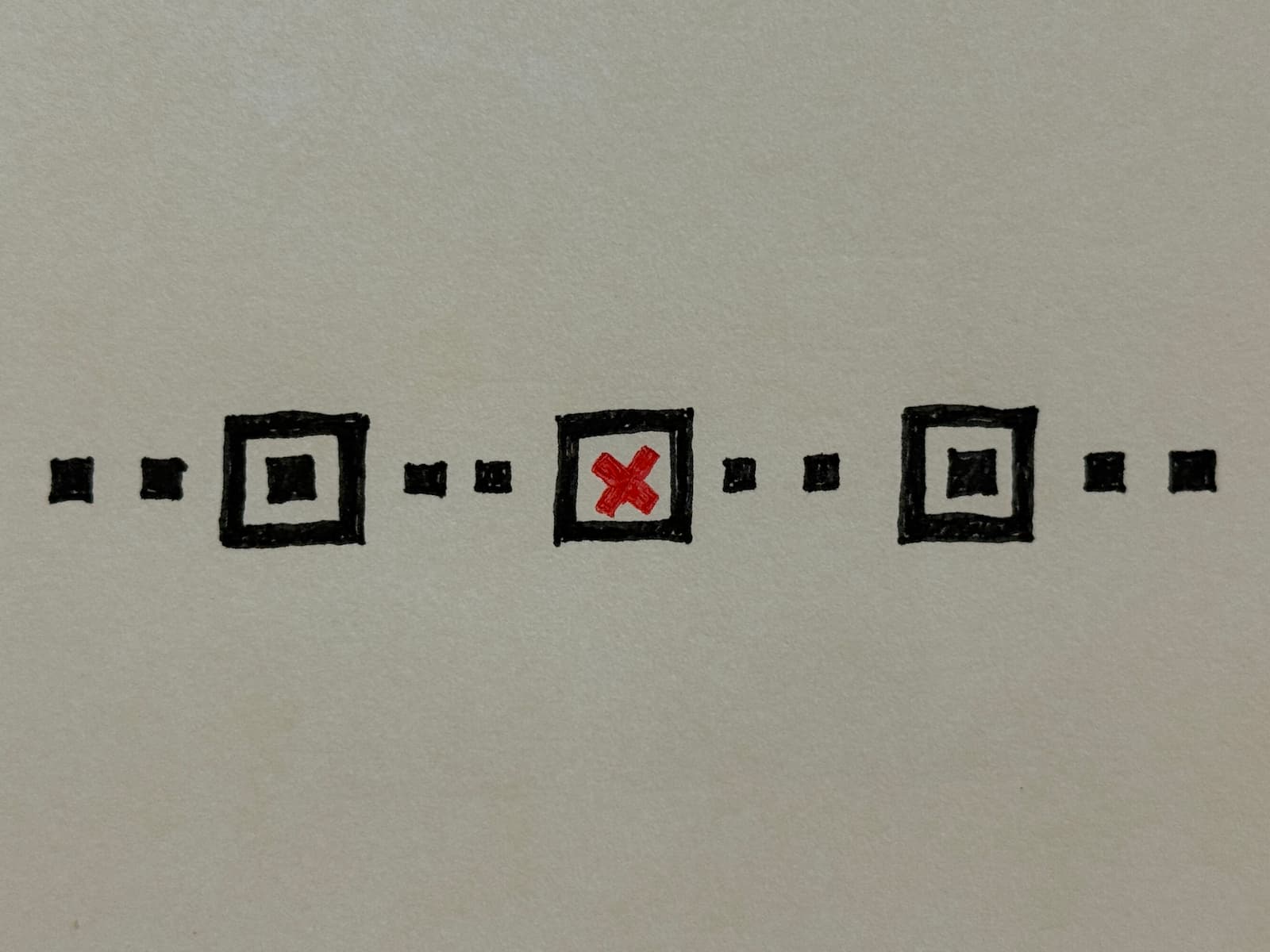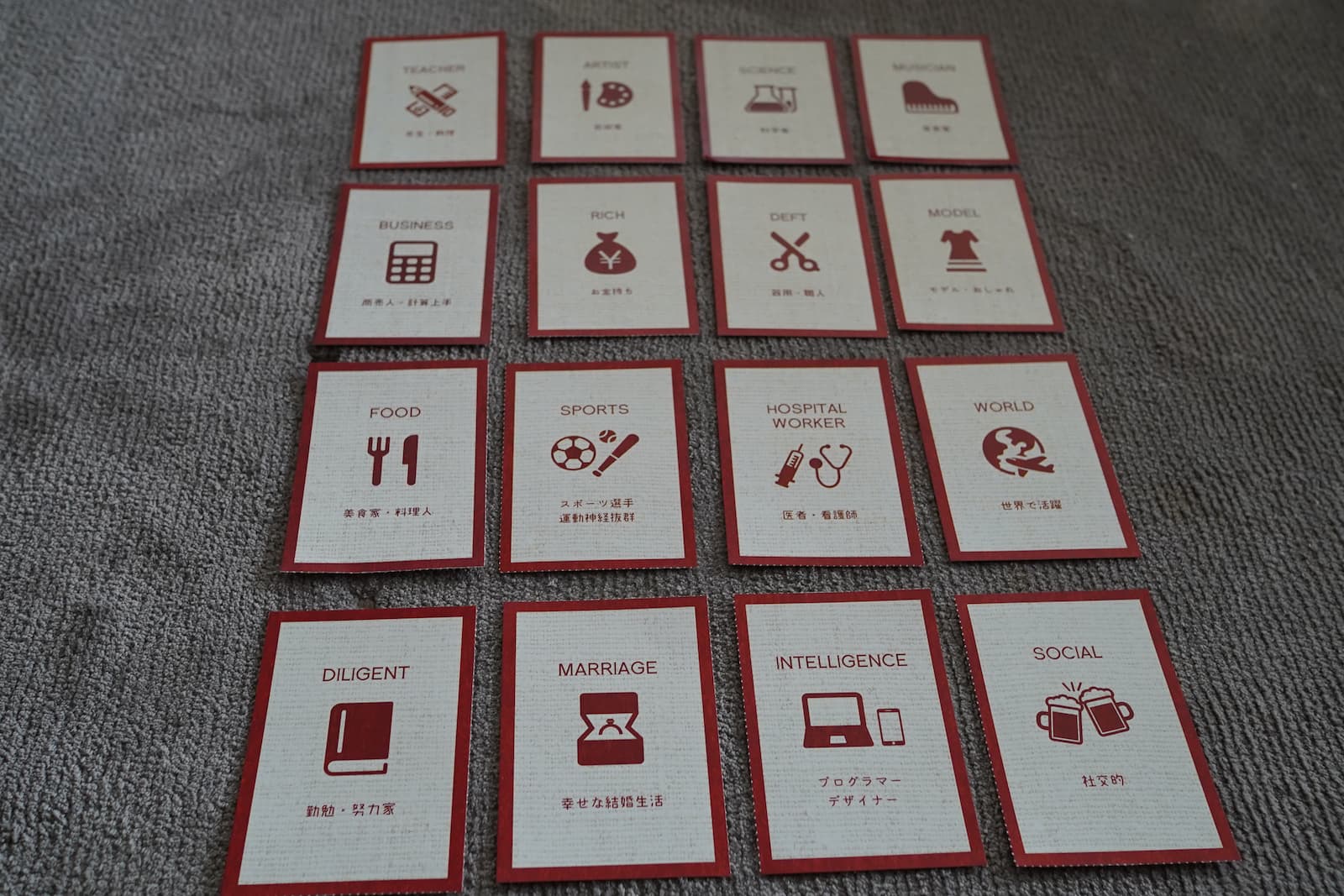昨日の記事では、PayBやモバイルレジなどのスマホ決済アプリを使っての地方税などの支払いについて書きました。
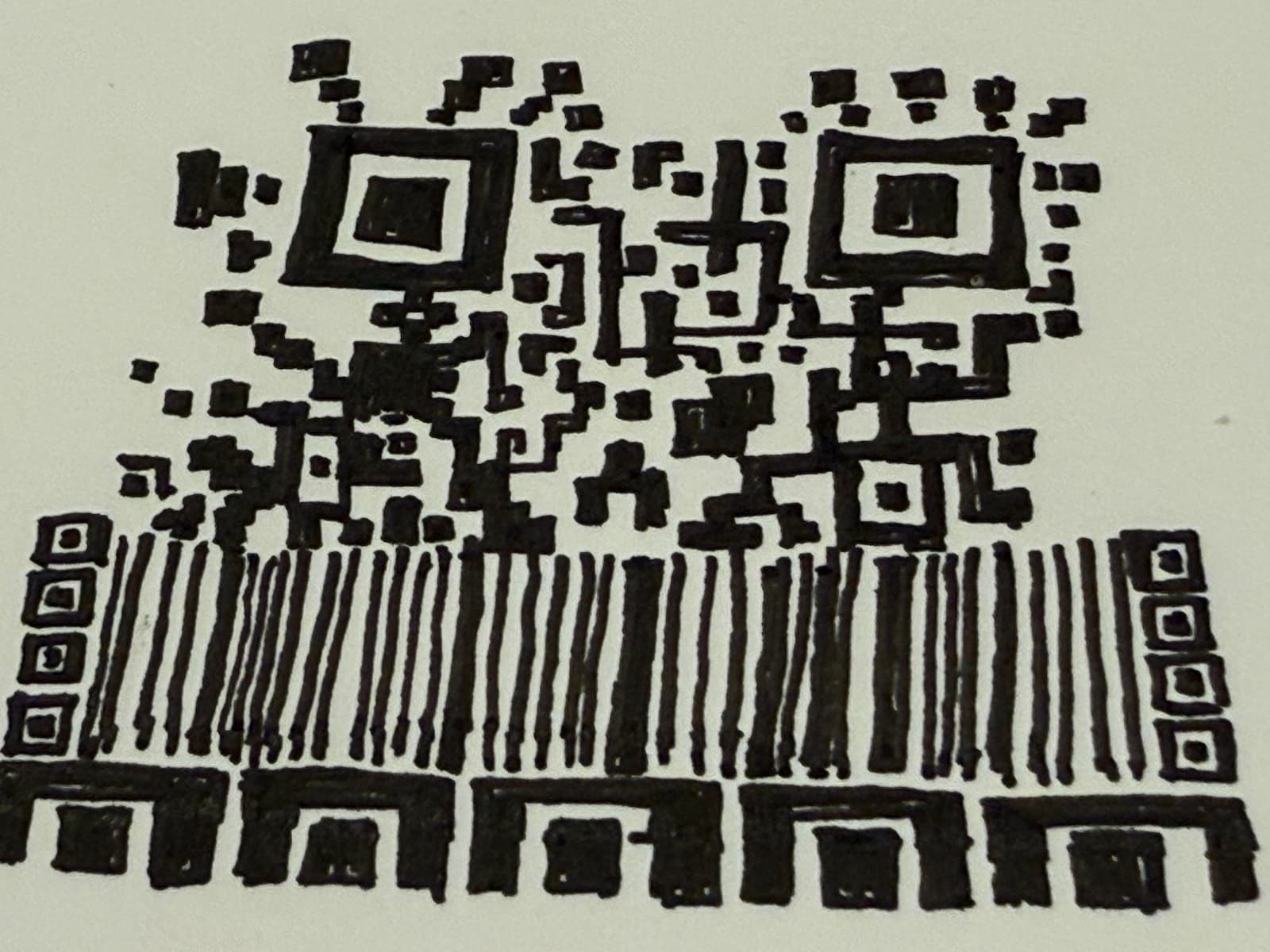
便利なスマホアプリ決済ですが、いくつか注意点もありますので今回の記事で紹介していきます。
領収書が出ない
スマホで支払うと、もちろん紙ベースの領収書などは発行されません。
手元に納付書がそのまま残るのみです。
元の納付書の日付欄も空白のままなので、いつ払ったか・まだ払ってないのかなどは見て分かりません。
領収証が無いと支払ったことの証拠書類がないということになるので、経費として計上する際などに困ることになります。
個人でスマホアプリ納付できる税金で、経理上、租税公課として計上できるものとしては次のようなものがあります。
・個人事業税
・固定資産税(事業用物件にかかるもの)
・自動車税(事業用の車両にかかるもの)
領収書の代替として、アプリで支払ったときのスクリーンショットやメールでの通知などをデータで保存しておいたほうが良いでしょう。
二重払いの危険性がある
前述のように紙の納付書は収受印も無いままそのまま残るので、既に支払った納付書を残しておくと、誤ってもう一度払ってしまう危険性があります。
自分でチェックマークを付けたり納付した日をメモしておき、「支払済」であるというのが一目で分かるように
なお、昨日の記事ではアプリで各種納付書のバーコードとeL-QRの読み取り実験を行いました。
その際、払い済みの納付書をeL-QRのコードで読み込むと、既に支払っていることのアラートが出ました(バーコード読み取りでは出てきませんでした)。
納税証明書の発行に時間がかかる
納税証明書というのは、税金を納めたことを証明する公的な書類として役所に発行してもらうものです。
スマホアプリ納付で納付した場合、この納税証明書が発行できるようになるまでに通常より時間がかかることになります。
東京都の説明ではバーコード読み取りの場合は納付から1週間程度、QRコードの場合は1ヶ月程度しないと納税証明書が取れないと記載されています。
納付してすぐに納税証明書が必要なときは窓口で支払う方が良いでしょう。
納税証明書が書類として必要になるタイミングとしては次のようなものがあります。
・自動車税の納付直後に車検を受けるとき
・補助金や助成金を申請するとき
・住宅ローンや融資を申し込むとき
バーコード読み取りは30万円を超える金額の納税には使えない
バーコード読み取りによるスマホ決済が使えるのは金額が30万円以下の納付書のみです。
30万円を超える納付書にはそもそもバーコードの記載がありません。
役所に連絡すると30万円以下の金額に分割した納付書を送ってくれることがあります(国税ではそういうことはできません)。
全国どこでもやってくれる確証はありませんが、東京の区によっては分割対応を行っている旨を区のサイトに記載していることもあります。
(例)港区、足立区、文京区など
まとめ
スマホアプリ納付にまつわる注意点を紹介してきました。
基本的には窓口などで支払うより手間も時間もかからないのでおすすめなのですが、証拠書類としての管理には注意が必要です。
すぐに納税証明書や領収証などが提出書類として必要な場合は、面倒でもスマホアプリ納付にこだわらず、窓口などで支払うのもアリでしょう。
金額が30万円を超える高額の場合は、自治体によって分割対応してくれる場合がありますが、その分アプリで納付する作業の回数は増えることになります。
状況と手間に応じて、そのときに最適な方法を選びたいものです。